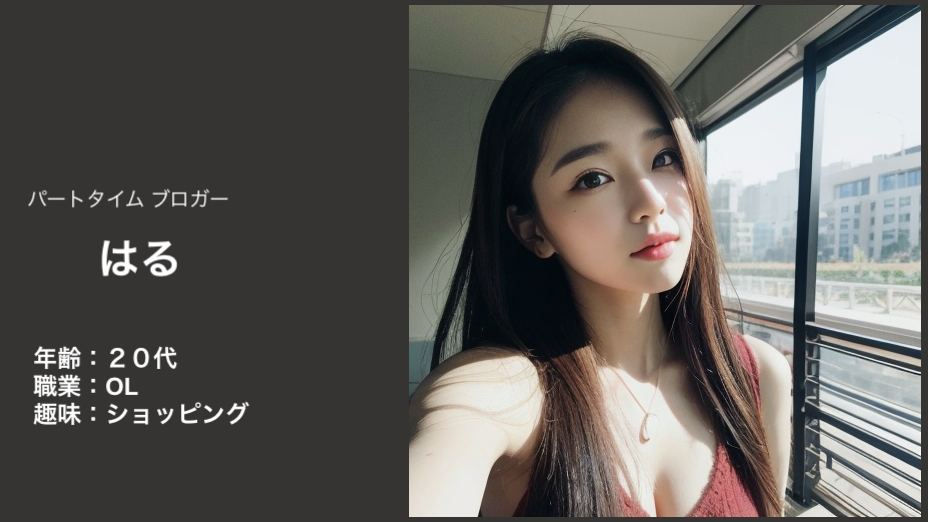こんにちは、みんな!ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、はるです。今日はちょっと面白い話をしたいと思います。お題は「色の認識」。私たちが日常で見かける色、赤や青、緑。これらの色は同じように感じているのかなぁ?そんな疑問を持ったこと、ある人も多いかもしれませんよね。(^_^)
最近、東京大学の研究チームが発表した研究が注目を集めているみたい。なんと、色の感じ方を科学的に分析して、「同じ色を見ているかどうか」を探ろうとしたらしいの! これは、色の認識が私たちの内面的な体験に依存しているため、本当に興味深いテーマだと思うの。
実験には426人の色覚正常者と257人の色覚障がいがある方、合わせて683人が参加したとか。参加者たちは、93種類の色から7つのペアを選び、それがどれだけ似ているかを評価していくんだって。8段階という評価法があるんだけど、果たして色ってどうやって判断するんだろう? 私もこの実験に参加してみたかったなぁ~!
で、研究チームはこの評価をもとに各グループの「色類似度構造」を作成したそうです。これは、その93種類の色がどのように関連し合っているのかを示すもの。実験結果から、まず色覚正常者同士のマップを比較したとき、正しく色を判断できた確率が51%だったって。偶然が1%なのに対して、51%って結構高いよね!こんなにみんな似たように色を感じているなら、ちょっと安心したりするかも。
一方、色覚障がいを持つ方同士でも、正しく色を判断できた確率は57%と高かったそう。でも、そこからさらに驚くべきことがわかったの!色覚正常者と色覚障がいを持つ方のマップを比較したところ、なんと正しく対応した確率がわずか3.8%だったという。え、そんなに差があるの?色覚障がいの方のマップでは赤と緑が近い位置にあるのに対して、色覚正常者のマップでは遠くに離れているっていうのがまた衝撃的。
この結果から言えるのは、同じ色覚タイプの人々は色の関係性をほぼ同じように感じているけど、異なる色覚タイプの人々は根本的に異なる色の関係性を持っているということなんだって。例えば、色覚正常者が「赤」と呼ぶ色は、他の色覚正常者にとっても同じ認識を持っているけれど、色覚障がい者の「赤」とは全然違う経験なんだよね。これは本当に面白い話!私たちの日常生活における色の認識がどれだけ主観的か、っていうことを考えさせられるよね。
色つながりで、最近私の友達が「この色合いは素敵よね!」って言って、色の話で盛り上がったことを思い出したんだけど、その時に何色かを例にして「これ、みんなの感じ方はどう?」って聞かれたらトンチンカンになることもありそうだなぁって感じたの!色って本当に人それぞれの感情や思いも反映されるから、面白いよね(*´ω`*)。
色の世界って、ほんとに奥が深くて、考えれば考えるほど新しい発見があるんだなって感じる。例えば、カラフルな洋服を見て「これ素敵!」って言っても、もしかしたら別の人は「全然ダメ」って思ってたりするかもしれない。どうしてそうなるのか、ちょっと科学的に分析されている今の時代ってすごいなぁって思ったり。
色覚の差異についてもっと理解することで、私たちのコミュニケーションも豊かになるかもしれないよね。色の感じ方の違いを理解することで、互いの価値観や捉え方を尊重できるようになるのは、すごく素敵なことだと思うな。お互いに素敵な色を持ち寄って、自己表現をもっと楽しめたらいいなぁって思っています。
本当に「色」って言葉で言い表せない素晴らしい体験だなーなんて、今回の研究を通じて再認識しました。これからも、色を通してのコミュニケーションを大切にしていきたいなぁ。みんなも色のことについて考えてみてね~!それでは、またね☆