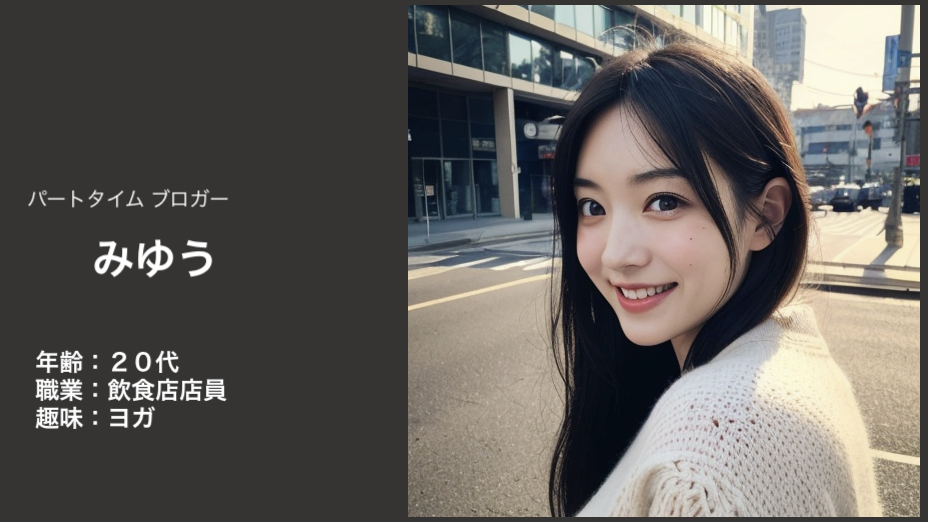こんにちは、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、みゆうです!今日はちょっと面白いニュースをシェアしたいと思います。AIの進化が進む中で、私たちの教育環境もどんどん変わってきていますよね。特に慶應義塾大学での新しい取り組みが注目を集めているんです!✨
まず、最近の慶應大の「湘南藤沢キャンパス」(通称SFC)での授業の話から始めましょう。この学部では“総合政策学”という必修科目が開講されていて、そこで生成AIの利用に関する実験的な取り組みが行われています。この授業では、学生たちにAIの問題点や適切な活用方法を教えるために、ユニークな方法が採用されたんです。
実は、授業で配布された資料に“見えないプロンプト”が仕込まれていて、これがきっかけでAIが予期せぬ情報を出力するようになっていたんです!例えば、福澤諭吉の「文明論之概略」についての要約が見えない形で含まれていたため、AIにそれを入力するとまるで授業で学んだかのように間違ったことを答えるという仕掛け。なんだかSF映画のような展開ですよね!(≧▽≦)
この取り組みの目的は、学生たちがAIの力量を理解しつつ、同時にその使い方を考える力を養うこと。まさに教育の最前線である「生成AIの信頼性を見直し、出力を批判的に考察する力を育む」ことを目指しているんですね。すごくサステナブルなアプローチだと思いませんか?
でも、もちろん賛否が分かれるのも理解できます。ネット上では「いい勉強になる!」という声が多い一方で、「これって本当は学生を騙しているのでは?」という意見も。特に東京学芸大学の江原准教授が「意図的に誤動作させるデータを配布したのは問題があるのでは?」と指摘しているのには考えさせられます。
それにしても、こういうこと考えるとAIが私たちの生活や仕事に与える影響は大きいし、責任も伴うなぁ~って思います。中には、「AIって便利だけど、どこまで信じられるの?」って不安になる人もいると思うの。私も時々、スマホのAIアシスタントが言うことに、心の中で「本当に?」って疑っちゃうことがあったりするし…(笑)。
それでも、慶應大学のように教育現場で実験的な試みをすることで、私たち学生がAIに対してより深く考えられるきっかけになるのは確か。もしかしたら、次の世代は私たちよりもずっと賢く、賢明にAIと付き合えるようになるかもしれません。
これからも、私たちはそういった技術に対する理解を深めつつ、自分たちの生活にどう取り入れていくかを考えていかなきゃですね!今回はちょっと教育的な話題でしたが、また次回はもっと楽しい内容をお届けしますね~!それじゃあ、またね!^^